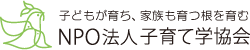チャイルド・ファミリーコンサルタント(CFC)とは
家族に寄り添い、親子の健やかな成長を支援する「育ちあいの専門家」です。
大人の「らしさ」も子どもの「らしさ」も大切に
それぞれの家族に合わせた「家族づくり」をサポートします。
CFCの活動
子育て学協会について
子どもが心身ともに健やかに成長するには、どんなことが大切なのでしょうか?
わたしたちがたどり着いた一つのこたえは、 子育てを今だけのものでなく、
子どもの将来につながるものと捉え、子どもたちの育ちのプロセスに合わせて
適切にかかわること。
そのために私たち大人が、子どもの育ちのプロセスに興味を持ち
学びを深めていくことが大切だと考えています。
幼児期の子どもにとって関わる大人や一番身近な社会である家族のあり方は、
将来の人格形成にも影響を与えるものです。
大人が子育てについて学び、子どもと一緒に成長していく「育ち合い」は、
青年期に起こる家庭内暴力や無気力などの問題行動を予防する
「発達予防学」という観点でも重要だと考えています。
子育て学協会は、家族に寄り添い、親子の健やかな成長を支援する
「育ちあいの専門家」の養成と、子育てに関する講座や情報の提供を通じ、
大人と子どもが共に「らしさ」を大切にできる社会を創ることに
貢献するNPO法人です。
Vision
「子育てに関わる保護者や人の成長」と
「豊かな心と言葉を持つ子どもたちの育成」を実現し
人を大切にする社会を目指す。
Mission
「幼児期の子どもたちが心身ともに健康に育つために必要な、
子育てに関わる人々の意識改革・成育環境の向上」
*NPO法人子育て学協会は、設立母体である㈱アイ・エス・シーともにvision・missionを共有しています。
子育て学会長 山本直美について

山本直美
NPO法人子育て学協会 会長
株式会社アイ・エス・シー 代表
幼稚園教諭を経て、大手託児施設の立ち上げに参画
1995年 株式会社アイ・エスシー(保育施設等を運営)を設立
2008年 これまで研究・実践してきた理論・プログラム普及のため、NPO法人子育て学協会を設立
2021年 らしさ研究所を設立 所長に就任
- 絵本を活用した独自教育プログラム
- 子育ての専門家『CFC(チャイルド・ファミリーコンサルタント)』の育成
- リクルート社事業所内保育所『And‘s』、認可・認証・小規模保育所『ウィズブック保育園』『リトルパルズ保育園』の運営
(東京・神奈川22園、名古屋10園 *2022年現在) - 児童発達支援施設『コペルプラス』の運営(東京1園、名古屋3園 *2022年現在)
- 企業内研修、パパママ向け講座、キッザニアプログラム監修、育児関連書籍出版